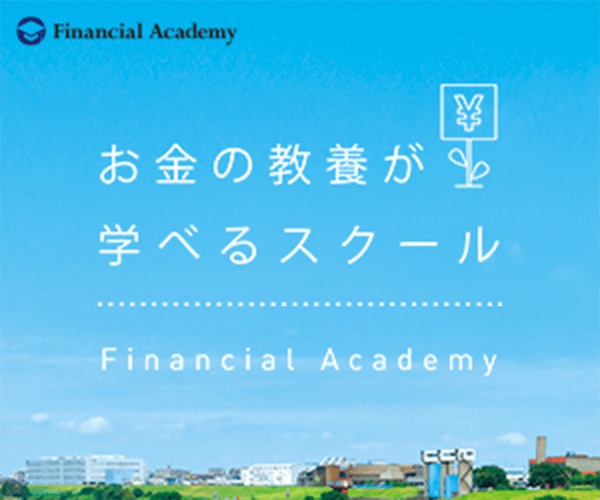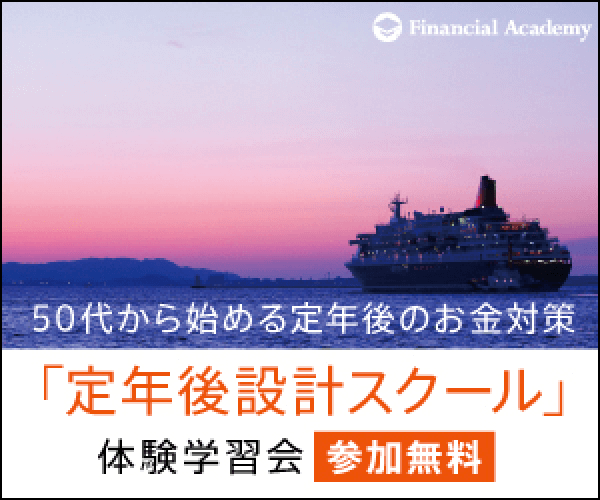こんにちは、億持ってない億男です。
会社員として働いている方の多くは、通勤にかかる費用を補助する「通勤手当」を受け取っているかと思います。しかし、最近ではSNSなどで「通勤手当にも税金がかかる」という話題を目にすることも増えてきました。
「会社から支給される通勤手当は全額非課税ではないの?」
「マイカー通勤の場合、税金の扱いはどうなるの?」
こうした疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、通勤手当と税金の関係について詳しく解説します。
通勤手当とは
通勤手当とは、会社が従業員に支給する、自宅から会社までの通勤にかかる費用のことです。ここで注意したいのは、「交通費」と「通勤手当」は異なるものだという点です。
通勤手当も交通費も移動にかかる費用なので、つい同じ物だと考えてしまいますが、実は違うのです。
通勤手当と交通費(出張・営業等)は、似ているようで異なる性質を持っています。
通勤手当は、自宅から会社までの移動にかかる費用であって、会社から支給される手当です。これは、毎日の通勤にかかるガソリン代や電車代などのことですね。手当ではありますが、一定額以上は課税対象となります。この点に関しては後述しますね。
一方で、交通費(出張・営業での移動にかかる費用)は、業務を行うための移動にかかる費用を指します。出張の旅費や営業のために発生した移動費用が該当します。これらの交通費は、業務を行うために必要な経費ですので、原則として非課税です。
つまり、定期的な通勤にかかる通勤手当は一定額を超えると課税されるのに対し、業務のために発生する交通費は非課税扱いになるという違いがあります。
通勤手当は上限額を超えると課税される
通勤手当に関しては、一定額を超えた場合は課税の対象になります。
公共の交通機関(電車・バス)を利用している場合は1ヶ月あたり15万円までであれば非課税となります。
例えば、会社から支給される通勤手当が10万円 の場合は 全額非課税です。ですが、会社から支給される通勤手当が17万円の場合 → 15万円を超えた2万円が給与所得として扱われるため課税対象となっています。
そして、マイカー通勤の場合は移動距離で課税されるかかがきまります。
(出典:国税局)
| 片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
| 2キロメートル未満 | (全額課税) |
| 2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
| 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
| 15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
| 25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
| 35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
| 45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
| 55キロメートル以上 | 31,600円 |
通勤距離が片道15キロメートルで、会社から2万円の通勤手当が支給されている場合、非課税限度額(12,900円円)を超える7100円分は課税対象になります。
ガソリン価格に重い税金が課されているにもかかわらず、通勤手当として支給されているガソリン代にも上限額を超えた場合にさらに所得税が課税されているということになります。
参考:国税局 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
マイカー通勤の非課税の上限が2025年秋から上がる予定
マイカー通勤をしている人の非課税の上限額に関しては、ガソリン価格の上昇に対応して、2025年秋から11年ぶりに増額することが検討されています。
確かに、ガソリン価格はこの数年で上昇しており、現在の非課税の上限額ではガソリン価格に対応しきれないというのは事実でしょう。マイカーで長距離を通勤している人にとってはこの対応は朗報と言っていいかもしれません。
この限度額がどの程度になるのかは未定ですが、詳細については、正式な発表を待つ必要がありますが、予定通り上限額が引き上げられれば現在よりも負担が軽減されることになるはずです。
まとめ
通勤手当は、会社が従業員の通勤にかかる費用を支給する手当です。ですが、一定の限度額を超えると手当ではなく給与となり課税対象になります。公共交通機関を利用する場合は1ヶ月15万円まで、マイカー通勤の場合は通勤距離に応じて非課税限度額が設けられています。この限度額を超えた金額には課税されます。
一方で、出張や営業など業務上の移動にかかる交通費は、業務遂行上の必要経費とみなされるため原則非課税です。
また、2025年秋からマイカー通勤の非課税限度額が引き上げられる予定であり、長距離通勤者の負担軽減が期待されています。
通勤手当の課税ルールや非課税限度額を確認して、この秋に予定されている上限額の引き上げに関しても注目していきましょう。