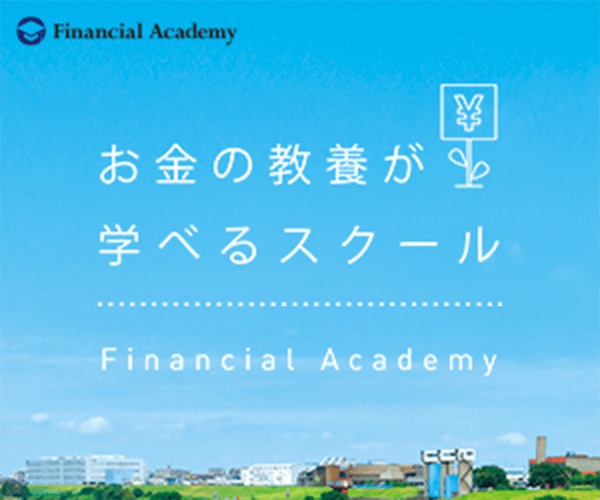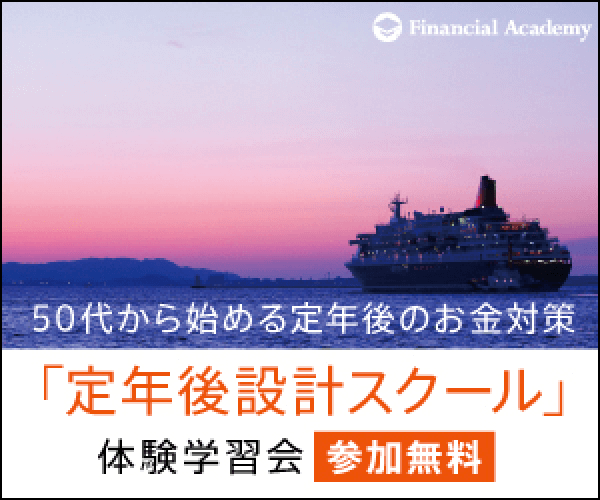こんにちは、億男です。
老後のお金は何かと心配ですよね。寿命が伸びるというのに、年金はきちんともらえるか分からないし、医療費の自己負担も上がる可能性があります。
そんな老後のために今から少しでも稼いでおきたいもの。そして実は老後のために効率的にお金を増やす方法があるんです。
iDeCoという言葉をきたことはありませんか?
実はiDeCoを使ってお金を積み立てると効率的にお金を増やすことができます。
今回はiDeCoを使ってお金を増やす方法を紹介します。
1.iDeCoとは
iDeCoとは、「個人型確定拠出年金」のことで、自分で毎月お金を拠出して自分の将来の年金のために積み立てていく制度です。
積み立てられる額は、職種によって以下のように異なります。
・会社員:23,000円
(ただし勤務先に”企業型確定拠出年金”がある場合は12,000円)
・自営業:68,000円(小規模企業共済と合算)
iDeCoに加入するためには、銀行や証券会社などの金融機関で申し込みの手続きが必要で、勤務先にも申し込み書類の一部を記載してもらわなければなりません。
そして最大の特徴は、拠出したお金の運用先を自分で指定する点です。
運用先として指定できるのは、以下の種類があります。
・投資信託
・定期預金
・年金保険
特に投資信託は、数ある商品の中でも、手数料が安くパフォーマンスも高い厳選された商品から選ぶことが可能。
このため投資の初心者でも安心して始めることができます。
2.iDeCoでの稼ぐための金融機関の選び方
iDeCoで稼ぐためには、適切な金融機関を選ばないとお金が効率的に増えていきません。
金融機関によって、iDeCoの手数料が大きく異なるからです。
iDeCoに加入して、毎月掛け金を拠出していくと、毎月の手数料が発生しますが、その中でも「口座管理手数料」が加入する金融機関によって異なります。
正確に言うと「国民年金基金連合会」と「信託銀行」に毎月支払う手数料167円はどの金融機関でiDeCoに加入しても支払わなければなりません。
しかし中には、加入する金融機関に口座管理手数料の支払いが必要なところもあるので、避けましょう。
口座管理手数料が無料なのは、SBI証券や楽天銀行などのネット証券で、逆に手数料が高額なのはメガバンクや地銀などの銀行です。
iDeCoに加入する際は、ネット証券などで加入し、口座管理手数料を無料にすることで、効率良くお金を増やせます。
3.iDeCoで稼ぐための商品の選び方
iDeCoで投資するときは、投資信託で信託報酬の低いものにしましょう。
そもそも投資信託とは、自分の代わりに投資会社ファンドマネジャーが株式や不動産などに投資する仕組みで、信託報酬とはその投資会社に支払う手数料です。
信託報酬は毎年発生するため、これが高いとお金がなかなか増えていきません。
ちなみに投資信託の中で信託報酬が低いのはインデックスファンドです。
インデックスファンドは、相場の動きに沿って堅実に投資していくもので、積極的に利益を狙いにいくアクティブファンドとは対をなします。
インデックスファンドでも毎月積み立てて投資を行うことで十分利益が狙えるので安心してください。
ちなみにiDeCoでは、元本確保型の定期預金もありますが、選ばないようにしましょう。
元本確保型の商品は、増えることも減ることもないのですが、毎月の口座管理手数料は同じく必要ですので、その分だけマイナスになります。
特に銀行など、口座管理手数料が高い金融機関で元本確保型の商品を選ぶと損しかしないので注意しましょう。
4.iDeCoで節税する
iDeCoに加入すると、掛けた金額の分だけ課税される所得から控除され、所得税や住民税などの税金が安くなります。
たとえば、iDeCoで毎月20,000円の掛け金を払っていると年間で240,000円。
この額が1年間で得た収入から丸々差し引かれて税金が計算されます。
仮に所得税の税率が5%だった場合、12,000円の節税、住民税の税率10%なので、24,000円の節税、合わせて36,000円も節税できます。
似たようなものに生命保険料控除がありますが、生命保険に払ったお金全てが控除されるわけではありません。
支払額に応じて控除額が変わる上に、上限があります。
このため、生命保険よりも高い節税効果があるので、さらにお金を増やすことができます。
5.iDeCoの注意点
iDeCoは始める際は、以下の点に注意しましょう。
・iDeCoで積み立てたお金は、60歳まで引き出すことができない
・投資なので損をする場合もある
・加入の手続きが少し面倒
6.まとめ
iDeCoは、低いリスクで投資でき、節税効果もあるため、かなり効率よくお金を稼ぐことができます。
これからは、銀行にお金を預けてもお金は増えず、国の年金にも期待できない時代ですので、自分で少しずつ勉強して投資を始めるのがおすすめです。
まだ投資をしたことがない人にもおすすめできるので、ぜひ始めてみてはいかがでしょうか。