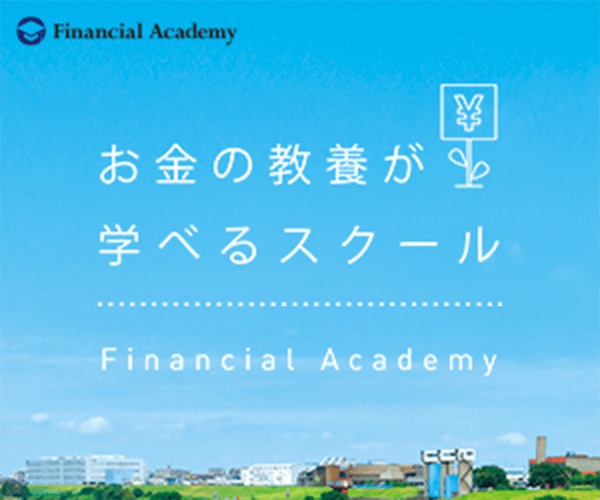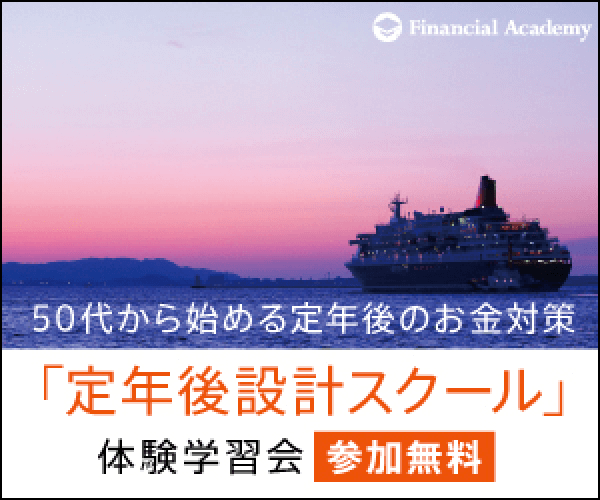こんにちは、億持ってない億男です。
ニュースや国の政策の話題で「給付付き税額控除」という言葉を耳にしたことはありませんか?聞き慣れない言葉に思えるかもしれませんが、実はこの制度は「減税」と「現金給付」という2つの仕組みを組み合わせた、支援制度です。高市早苗内閣総理大臣が掲げている政策でもあります。
この「給付付き税額控除」は簡単に言えば「税金を納めていない人には給付」「税金を払っている人は減税で実質的に手取りを増やす」という仕組みです。つまり、所得が低い人も公平に支援を受けられるようにする制度なのです。この記事では、この給付付き税額控除の仕組みやメリット、注目される理由をわかりやすく解説します。
給付と減税のハイブリッド
従来の税額控除は、所得税の納税額を減らすというものです。たとえば、1万円分の税額控除を受けられる人が5万円の税金を納める場合、税金の支払いは控除額を引いた4万円になります。これが控除の考え方です。
つまり、本来であれば支払うはずだった1万円に関しては所得として手取りに含まれるのです。
しかしこの制度では、所得が少なくもともと納める税金がほとんどない人は恩恵がありません。仮に、納税額が5,000円しかないのに、1万円分の控除を受けても、減税できるのは5,000円まで。残りの5,000円は控除しきれず、結局、最大限に恩恵を受けられないことになってしまいます。
そこで登場するのが「給付付き税額控除」です。この制度は控除しきれない分を「現金で支給する」仕組みです。つまり、納税額が少なくても、本来控除されるはずだった金額がまるまる現金で受け取れるようになります。
そして、税金を支払っている人は「支払うべき税金が少なくなる」手元に残るお金が多くなるということになります。
現金をもらえる人と減税になる人がいる
給付付き税額控除では、対象者によって受け取り方が変わります。
所得がある人は今まで通り「税金を減らす」という形で税金の控除の恩恵を受けます。一方、所得が少なく納税額が少ない人やまたはゼロの人は「差額分を現金で受け取る」という形になります。
つまり、高所得者にも低所得者にも、公平に支援が行き渡る仕組みなのです。従来の給付は非課税世帯や子育て世帯など特定の条件を満たす人のみに給付されていましたが、給付付き税額控除では税金を支払っている人にとっても「減税」という形での恩恵があります。
日本でも、所得格差の広がりや物価高騰の影響を踏まえ、より公平な支援のあり方として、この制度が注目されています。
今までの給付より不公平感が少ない
前述したとおり、給付付き税額控除は不公平感が少ない支援が可能です。税額控除という仕組みをベースにすることで、支援額がより適切に振り分けられ、必要な人に手厚く届くようになります。
もちろん異論は多々ありますが、少なくとも非課税世帯のみや子育て世帯のみという限定的な支援よりは不公平感が少ないのは事実です。
また、税金の仕組みと一体化しているため、申請手続きが比較的シンプルになりやすいという利点もあります。たとえば、確定申告の段階で自動的に控除額や給付額が反映される仕組みが整えば、余計な申請をせずとも給付が受けられるようになる可能性があります。
このように、給付付き税額控除は特定の人たちに限定した「ばらまき型の給付」と比べて不公平感が少なく、持続的な支援策として有効であると考えられています。
導入時に想定される課題
給付付き税額控除は公平性の高い制度といわれていますが、導入にはいくつかの課題もあります。
まず大きいのは財源の確保です。減税と給付の両方を行うため、国としてはかなりの支出が必要になります。特に低所得者への給付は毎年継続して行うことになるため、長期的な財政負担が課題になります。ただし、経済成長が見込まれるため、その経済効果で発生する税収で財源をまかなうことができるという意見もあります。
また、所得情報を正確に把握するために、確定申告などの手続きが増える人も出てくるかもしれません。制度をスムーズに運用するためには、国民にとっても分かりやすい設計が求められます。
まとめ
給付付き税額控除は、減税に「現金給付」という仕組みを組み合わせた支援制度です。本来であれば控除によって減らせるはずだった税金を、支払いきれない人には現金として支給するという点が大きな特徴です。
所得の高い人には税金の軽減という形で、所得の低い人には現金給付という形で、それぞれに合った支援が行き渡るよう設計されています。
従来のように一律で同じ金額を配る方式と比べて、不公平感が少なく、より実効性の高い支援策として注目されています。物価上昇や生活費の負担が重くなっている今、このような制度はますます重要性を増していくでしょう。