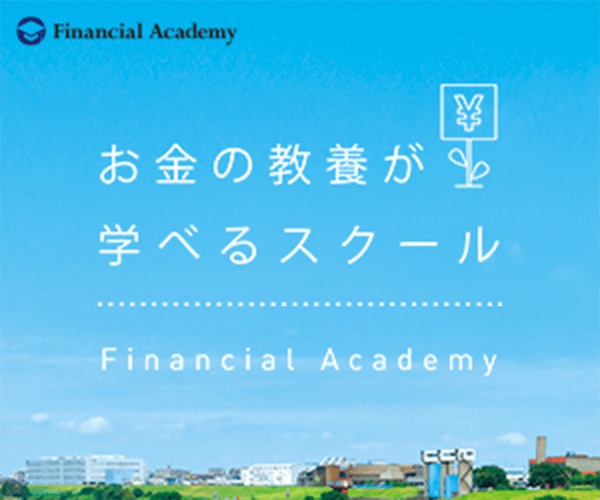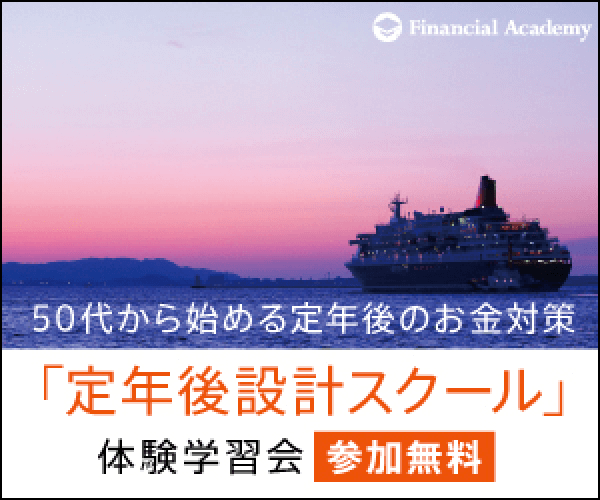こんにちは、億持ってない億男です。
年金は老後の生活を支えるための大切な収入です。そして、年金には、老齢基礎年金や老齢厚生年金といった基本的なものに加えて、一定の条件を満たすと上乗せして受け取れる仕組みがあります。そのひとつが「加給年金」です。名前は耳にしたことがあっても、実際にどんな条件で支給されていて、いくらもらえるのかを正しく理解している人は少なくありません。この記事では、加給年金の基本から金額、注意点まで、わかりやすく解説します。
加給年金とは
加給年金とは、厚生年金保険に20年以上加入していた人が65歳になったとき(または定額部分支給開始年齢に到達したとき)に、生計を維持している配偶者や子がいる場合に、老齢厚生年金に上乗せして支給される制度です。ここで注目するべきは「本人がどのくらい年金に加入していたか期間」と「扶養している家族の条件(年齢など)」です。
具体的には以下の通りです。
● 厚生年金の被保険者期間が20年以上あること
● 65歳到達時点(または定額部分の支給開始時点)で、生計を維持している配偶者または子がいること
また、65歳を迎えた時点でまだ加入期間が20年に達していなかった場合でも、その後、年金に加入し続けて加入期間がトータルで20年以上になれば、定時改定や退職改定などのタイミングで加給年金が加算されることがあります。
つまり、条件を満たしているにもかかわらず手続きをしないと支給されないため、忘れずに届出を行うことが重要です。
参考:加給年金額と振替加算 日本年金機構
加給年金の金額は?
加給年金の支給額は、子の人数や年齢によって金額が変わります。2025年度時点での支給額は次の通りです。
● 配偶者:239,300円(ただし65歳未満であることが条件。大正15年4月1日以前生まれの配偶者には年齢制限はありません)
● 1人目・2人目の子:各239,300円(18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害状態にある子)
● 3人目以降の子:各79,800円(同上)
子が複数いる場合には、人数によって加算される金額が変わるようになっています。
例えば、加入者が65歳になった時点で専業主婦の妻(65歳以下)と高校生の子どもがいる場合には、配偶者分と子ども分をあわせて約48万円が年金に上乗せされます。これは家計にとって大きな助けとなる金額です。
ただし、加給年金は自動的に一生もらえるわけではありません。次に説明するように、支給が終了するタイミングがあります。
加給年金は配偶者が65歳になると支払われなくなる
加給年金の最大の特徴は、「配偶者が65歳(この場合は18歳)になると原則として終了する」ことです。
理由は、配偶者が65歳になると、自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取る年齢となるため、配偶者から扶養されている立場ではなくなるからです。
そのため、夫が65歳の時点で妻が63歳であれば加給年金が支給されますが、妻が65歳に到達した瞬間にその分は打ち切りになります。つまり、加給年金をもらえるのは2年ということになります。
「加給年金がなくなったら生活が・・・」と感じるかもしれませんが、この場合は妻自身の年金が支給されることで世帯全体としての収入は維持されます。
ねんきん定期便は必ずチェックすること
加給年金の対象かどうかは、日本年金機構から送られてくる「ねんきん定期便」に記載されています。
ねんきん定期便には加入期間や見込額などが記されているため、毎年必ずチェックしましょう。もし記載内容に誤りや疑問があれば、早めに年金事務所に問い合わせるのがおすすめです。
また、加給年金の受給には請求手続きが必要です。自動的に支払われるわけではなく、条件を満たしていることを証明して申請する必要があります。提出書類としては、戸籍謄本や住民票、子どもの在学証明書などが求められる場合もあります。
届出をしないと本来もらえるはずの加給年金を受け取れないケースもあるため、忘れずに行いましょう。
まとめ
加給年金は、厚生年金に20年以上加入してきた人が65歳を迎えた際に、配偶者や子を扶養している場合に受け取ることができる年金です。配偶者が65歳未満であれば年間239,300円が加算され、さらに子どもについても条件を満たせば加算の対象になります。ただし、配偶者が65歳に到達(この場合は18歳)すると加給年金は終了し、受給を続けることはできません。加えて、加給年金を受け取るためには裁定請求と呼ばれる届出を必ず行う必要があります。
加給年金の対象になるかは、ねんきん定期便などで確認できます。ねんきん定期便で自分の加入状況や見込額を確認し、条件を満たしているなら早めに準備を整えておくことが大切です。手続きを怠れば、本来もらえるはずの年金が支給されない可能性もありますので、必ずチェックするようにしましょう。