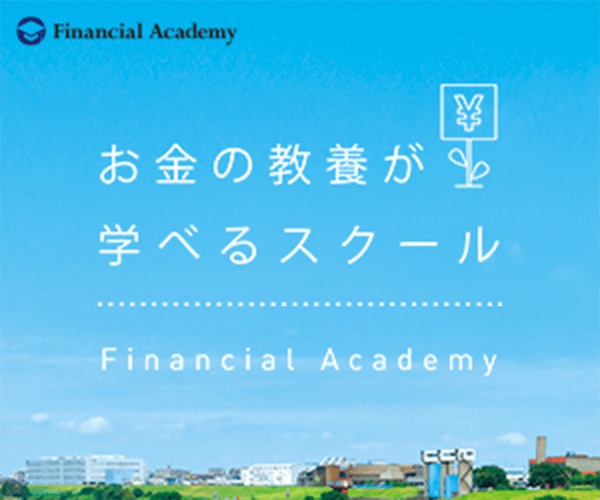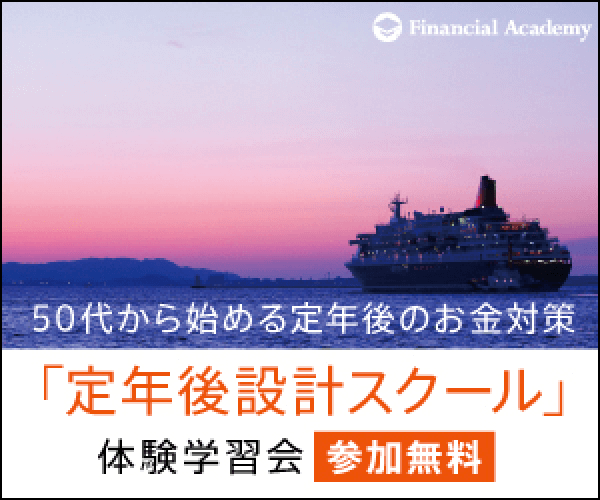こんにちは、億持ってない億男です。
この数年、値上がりしているガソリン価格に家計が圧迫されているという方も多いのではないでしょうか。ガソリン価格は市場の影響を受けて変動していますが、価格が高い理由はそれだけではありません。ガソリンにはいくつもの税金がかかっているため価格が高いのです。そして、ガソリンにかけられている税金のひとつである「暫定税率」が、いよいよ廃止されることになりました。ニュースでも大きな話題となっていますが、「車に乗らない人には関係ない」──そう思っている方も多いはずです。
しかし実は、この税率の廃止は 車に乗らない人にもメリットがある と考えられています。
今回は、暫定税率が廃止されるとどう変わるのか、そして暮らしにどんな影響があるのかについて、わかりやすく解説していきます。
ガソリンの暫定税率が廃止になる
まず、暫定税率とは「道路整備に充てるために一時的に上乗せされたはずの税率」のことです。しかし、その“暫定”状態が長年続き、結果としてガソリン税は実質的に高止まりしていました。
それがいよいよ次のスケジュールで廃止されます。
| 対象 | 廃止時期 | 価格の低下幅 |
| ガソリン | 2025年12月31日 | 1Lあたり 25.1円引き下げ |
| 軽油 | 2026年4月1日 | 1Lあたり 17.1円引き下げ |
さらに、この税金分にも消費税10%がかかっているため、実際には ガソリン価格は1Lあたり約28円ほどの値下げが期待できます。
例えば、50L入る車の燃料を満タンにした場合は「50L × 約28円 ≒ 1回の給油で約1,400円の節約」月に2回給油する人であれば、年間約3〜4万円の負担軽減 にもなる計算です。
これはかなり大きな変化ですよね。
車が必需品の地域では特に恩恵が大きい
都市部では公共交通機関が発達しているため、車は「持っていても持っていなくてもよいもの」という位置づけになりがちです。
しかし地方では、車は生活の足として利用されています。バス停や駅まで距離があったり、本数が少ない場合は公共交通機関を利用して移動するのは現実的ではありません。
・通勤
・買い物
・通院
といった日常生活の移動手段の多くが「車」なのです。
そうした地域では、ガソリン価格の影響は日々の生活コストに直結します。そのため、暫定税率の廃止は 地方ほどメリットが大きいと考えられています。
また、タクシー業・運送業・営業車を多く抱える企業にとっても、大きなコスト削減効果が期待できます。これは「会社の経費が下がる」という話では終わらず、やがてサービス価格や商品の値段にも影響する可能性があるのです。
車を持っていなくても恩恵がある
ですが、暫定税率廃止のニュースを聞いても「車に乗らない人にはまったく関係ない」という意見を耳にすることもあります。ですが、実はそうではありません。
物流コストが下がるとモノの値段にも影響するため、間接的な恩恵があるのです。
物流コストが下がるとモノの値段にも影響する
私たちが買っているほとんどの商品は、何らかの形でトラック輸送によって運ばれています。野菜・お肉・日用品・家電・衣類……など、そのすべてが ガソリン(軽油)を使って流通しています。つまり、ガソリンや軽油が安くなれば、運送会社の輸送コストが下がり
小売価格が下がる可能性があるという流れが生まれます。
たとえば、コンビニやスーパーの価格、ECサイトの送料などは、燃料費の影響を強く受けます。
つまり、ガソリン代が下がることは、結果的に 私たちの日常生活の価格負担を下げる働きがあるのです。暫定税率の廃止は車を持っていなくても、暮らしのあらゆる場面で恩恵があるということです。
公共交通機関の運賃にも影響
また、地域の路線バスやタクシー、配送車両もガソリンを使用しています。
燃料費が下がれば、運行会社が負担するコストも軽減されるため、運賃や料金改定の抑制につながる可能性があります。
とくに地方では、車を持っていなくても 「移動手段としての公共交通機関」に頼る人が多い ため、ここでも恩恵を受けやすいと言えます。
まとめ
ガソリンにかけられていた暫定税率は「一時的な措置」として導入されたものでしたが、長年維持されて、生活コストを押し上げてきました。今回の廃止でガソリンや軽油の価格が下がることで、自家用車を利用する人にとっては給油代の負担が軽くなります。特に、車が生活の中心となる地域では、その恩恵は日常の支出に直接影響します。
また、車を持っていない人にも影響があります。流通に使われるトラックや公共交通も燃料を使用しているため、燃料費が下がれば物流コストや運行コストの低下が期待できます。
つまり、暫定税率の廃止は単なる「車に乗る人だけのメリット」ではなく、社会全体に波及する効果がある政策といえます。