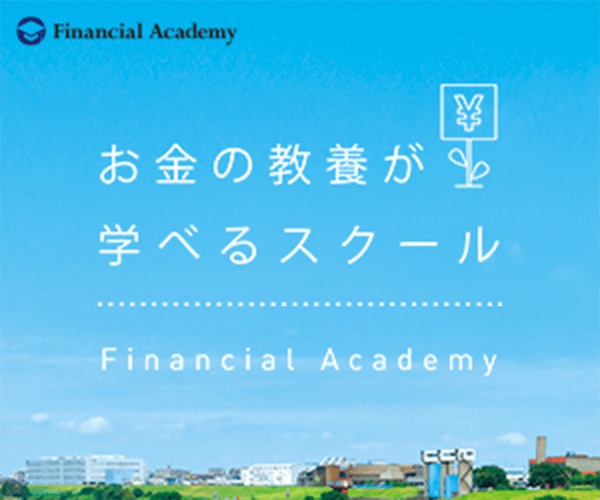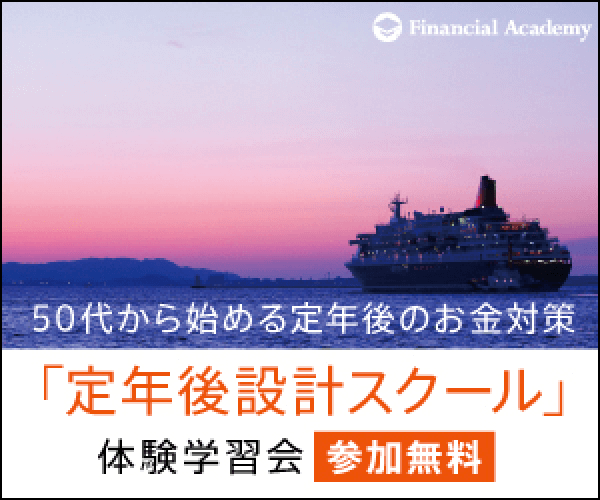こんにちは、億持ってない億男です。
「税金は払わなきゃと思っているけれど、つい後回しにしてしまう」「少しぐらい遅れても大丈夫でしょ?」そんな考えを持ってしまう人もいるかもしれません。ですが、税金の滞納は想像以上に重い結果を招くことがあります。
税金は国や自治体が法律に基づいて徴収するものであり、納税は国民の義務なのです。これは、銀行のローンやクレジットカードの支払いとはまったく別の仕組みであり、延滞が続くと強制的な差し押さえが行われることもあります。
今回は、税金を滞納した場合にどうなるのか、そして意外と知られていない「ブラックリスト」「自己破産」「相続放棄」との関係について解説します。
税金を滞納してもブラックリストにはならない
まず誤解されやすいのが、「税金を滞納するとブラックリストに載るのでは?」という点です。結論から申し上げるなら、税金を滞納してもブラックリストには載りません。つまり、税金の滞納がローンの審査に影響するということはないのです。
ブラックリストとは、リストがあるわけではなく信用情報機関に登録される「個人の信用取引履歴」のことです。主にクレジットカードやローンの支払いに関するデータが管理されており、大幅な延滞や債務整理などの情報が記録されます。一方で、税金の滞納は金融機関の信用情報とは関係がなく、クレジットカードの審査やローンの申込みに直接影響することはありません。
しかし、だからといって安心は禁物です。税金の滞納は「信用情報」ではなく「行政の権限」で管理されており、延滞すれば延滞金が加算され、最終的には財産を差し押さえられる可能性があります。
滞納期間が長引くほど利息のような延滞金が増えるため、早めの納付や相談が重要です。
もちろん、自治体や税務署は、いきなり強制執行を行うわけではありません。まずは督促状を送り、それでも支払いがない場合に口座や給与を差し押さえるという措置に入ります。
つまり、信用情報には影響しなくても、生活そのものに影響を及ぼすのが「税金の滞納」なのです。
税金は自己破産してもなくならない
意外と知られていないのが、税金は自己破産をしても支払い義務が残るという点です。
自己破産をすると、クレジットカードの借金やキャッシング、ローンなどの債務は原則として免除されます。自己破産のさいに裁判所が「免責」を認めれば支払い義務がなくなるためです。しかし、税金や健康保険料、年金保険料などの「公的債務」は、自己破産をしても帳消しにはなりません。税金は、免責の対象外とされています。他にも養育費など免責にならないものがあります。
ですので、自己破産をしても滞納している税金には延滞金も発生します。延長期間滞納を続けると、元金よりも延滞金のほうが多くなることもあるため、早期の相談と対応が必要です。
どうしても支払いが難しい場合は、税務署や自治体に「分納」や「納税猶予」を申し出ることができます。真摯に相談すれば、分割での納付計画を立ててもらえるケースもあるため、放置しないようにしましょう。
亡くなった人の税金の支払い義務は?
では、もし税金を滞納したままの人が亡くなってしまった場合、その税金の支払い義務はどうなるのでしょうか。
原則として、故人の財産や負債は相続人に引き継がれます。つまり、滞納している税金も「マイナスの財産」として相続の対象になります。この場合、相続人がその税金を支払う義務を負うことになります。
ただし、ここで重要なのが「相続放棄」という制度です。相続放棄をすれば、故人の財産も借金も一切引き継がないことになります。したがって、滞納していた税金の支払い義務もなくなります。ただし、相続放棄をすれば他の財産に関してもすべて放棄することになります。
そして、相続放棄の注意点として、相続放棄は相続が発生してから(相続の発生を知ってから)3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があるということです。故人の財産の一部でも使ってしまうと「相続を承認した」とみなされる可能性があるため、放棄を考える場合は早めに専門家へ相談することが大切です。
まとめ
税金の滞納は、信用情報には直接影響しないものの、放置すれば確実に生活へダメージを与えます。税金を放置すると延滞金が増え、財産の差し押さえに発展するケースも少なくありません。また、税金は自己破産でも免除されない特別な債務であり、逃げることができない義務です。
さらに、亡くなった後も相続の形で支払い義務が引き継がれます。ですが、相続放棄をすれば支払い義務を免れることができます。
税金は信用情報にこそ影響はないものの、強制力が強く、そして、逃げることができないものです。もし支払いが難しいと感じたときは、ためらわず税務署や自治体へ相談してみましょう。