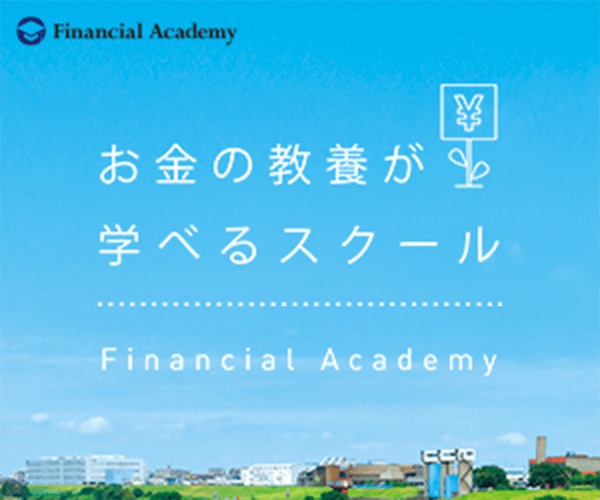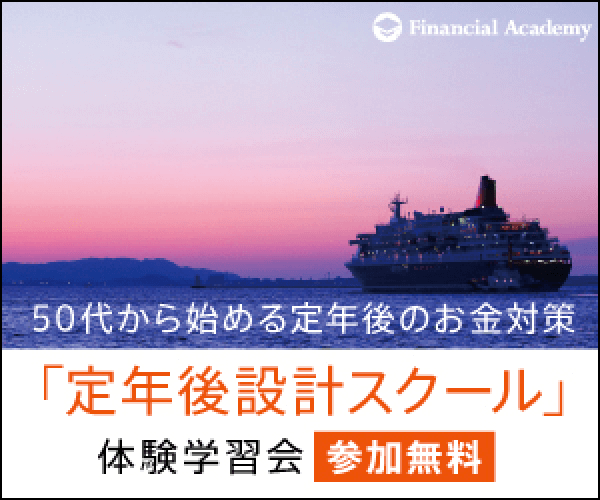こんにちは、億持ってない億男です。
フリーランスという働き方が定着している今、自分で仕事を受注しているというかたも多いでしょう。そして、仕事が軌道にのると「そろそろ個人事業主から法人化しようかな」と考えている方もいることでしょう。いわゆる“法人成り”です。法人化することには、節税や信用力の向上といったメリットがあります。
しかし、意外と見落とされやすいのが「保険の仕組みの違い」です。
特に雇用保険や失業保険について「法人にしたら自分も入れるのか?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?
今回は、株式会社の会社役員や合同会社の社員が雇用保険に入れるのかどうかを中心に、法人成り前に知っておきたい保険制度の違いを解説していきます。
役員や代表社員は雇用契約をしていない
まず、大前提として、株式会社や合同会社の代表者・役員といった立場の人は、会社と雇用契約を結んでいるわけではありません。役員や代表者「雇われている側」ではなく「雇う
側」として法人の経営を担う立場です。
個人事業主が法人成りした場合、自分が設立して代表者になるケースがほとんどです。
たとえば株式会社の場合は
・株主が役員を選任して委任する
・役員(取締役など)が会社を経営する
・従業員が雇用契約のもとで働く
という構造になっています。
一方、合同会社では少し表現が異なり、出資者=社員という呼び方になります。ただし、ここでいう「社員」は、一般的な意味での従業員ではありません。むしろ、株式会社でいう「株主兼取締役」に近い立場と考えておいてください。
つまり、株式会社でも合同会社になっても、会社とその代表者や出資した社員(いわゆるオーナーという人たち)は雇用関係にはないのです。
会社を成立したら「会社員になるような感覚」があるかもしれませんが、実際には代表者や役員は会社員ではなく委任契約(株式会社の場合)もしくは、出資者として職務を執行しているということになります。
役員は雇用保険に入れない
雇用保険は雇用されている人のための保険なので、役員や合同会社の社員は加入できません。個人事業主が法人成りして株式会社や合同会社の代表になっても、その会社で自分が失業保険に加入するということはないのです。
雇用保険は、雇用契約に基づいて労働をする人のための保険制度です。したがって、法人の代表や役員のように、雇用契約ではなく委任もしくは出資して「経営をしている」という場合は加入の対象になっていないのです。
これは、個人事業主が法人成りして、たとえば自分が代表取締役社長や合同会社の業務執行社員になった場合でも同じです。たとえ実際には「労働者のように働いている」といった感覚であっても、法的には“雇用されていない”ため対象外となります。
つまり、雇用保険に入っていない=失業給付が受け取れないということになります。会社が倒産した場合でも、失業手当はもらえません。
経営者はたとえ自分ひとりであっても「労働者ではなく経営者である」と見なされるのです。この点は個人事業主とあまりかわらないかもしれません。失業保険というセーフティネットの対象外となってしまうのです。つまり「会社にしたから、雇用保険に入って万が一に備える」ことはできないのです。
個人事業主の法人成りには様々なメリットがありますが、そのメリットに「雇用保険」は入らないということになります。
厚生年金は原則加入する
一方で、法人の代表者であっても、厚生年金と健康保険(=社会保険)については原則として加入が義務とされています。
これは「加入できる」というものではなく、加入が原則として義務という意味です。つまり、経営者になると「雇用保険には入れず厚生年金には加入する義務が発生する」というわけです。
厚生年金に加入するということは毎月の費用も発生します。厚生年金は2階建ての年金制度の重要な部分であり、将来の備えではありますが、厚生年金の支払いを把握して法人成りするようにしましょう。
まとめ
個人事業主から法人成りをすると、税制面のメリットや信用力の向上など、多くの利点があるとされています。しかしその反面「雇用されていない立場」であるということは個人事業主と同様で、労働者向けの保険制度の対象外になります。
雇用保険は雇用されている人のための保険制度ですので、雇用関係にない法人の代表者や役員(合同会社の社員)は加入できません。
つまり、事業がうまくいかずに会社を閉じた場合でも、失業保険は受給できないということです。
一方で、代表者や役員であって厚生年金や健康保険には原則として加入義務があるため、
「雇用保険には入れないけど、社会保険料はかかる」というアンバランスな状況になってしまうわけです。
法人成りを考える際は、こうした社会保険制度の違いを正しく理解したうえで、総合的に検討することが大切です。