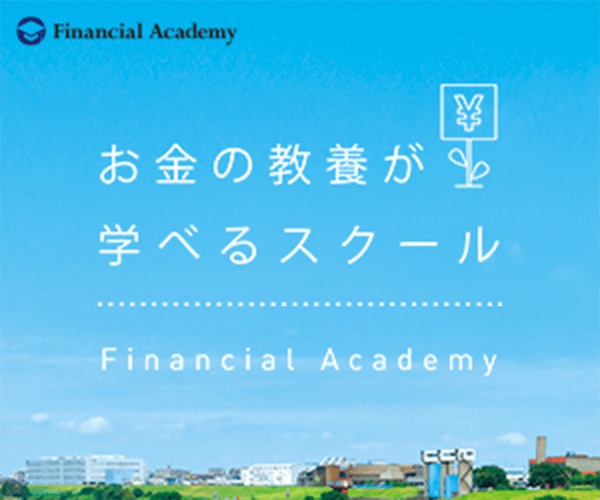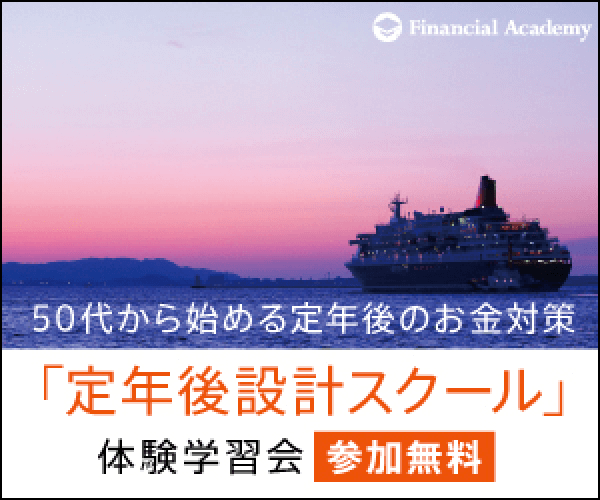こんにちは、億持ってない億男です。
最近では、キャッシュレス決済がかなり普及していて現金を使うシーンは減っていますが、それでも日常のいろいろな場面で現金を「誰かに渡す」という機会はあります。
たとえば習い事のお月謝、結婚式のお祝い、葬儀の香典などです。このような時には、それぞれに「お金の渡し方のマナー」があります。ローカルなルールや若い世代の方は知らないマナーもあるため「これはどうしたらいい?」と悩む方も多いでしょう。
今回は、お月謝や冠婚葬祭におけるお金のルールやマナーについて解説します。
お金を渡すときのルールやマナー
現金を手渡すときは、ただ現金をそのまま渡せばよいというものではありません。相手やシーンによって、一定のマナーを守ることで「気配りができる人」「常識がある大人」という印象を与えることができます。
たとえば、誰かに謝礼を渡す場合や先生にお礼をする場合、封筒に入れずに裸のまま渡すのはとても失礼とされます。習い事のお月謝なら「月謝袋」という専用の封筒を使うのが一般的で、教室側があらかじめ配布してくれることも多いですよね。そこに金額と名前を書いて提出するのです。もし専用袋がない場合でも、封筒に入れて渡しましょう。
もちろん、家族や親しい友人にその場で割り勘したお金を渡すようなカジュアルな場合は別ですよ。
また、もう少しこだわるのであれば、紙幣の向きや揃え方にも気を配ると丁寧さが伝わります。丁寧にしたいのであれば、封筒の中でお札の顔を上に揃えて入れるとよいでしょう。こうした、ちょっとした工夫で、受け取る側に好印象を与えられます。
習い事のお月謝は新札?
SNSでも話題になったのが「お月謝は新札で用意するのかマナーなのか」です。
これは、本当にローカルなルールであり人によって考え方が異なります。もちろん、きれいなお札を選んで入れるのが無難ではありますが、まったく気にしないところもあります。特に子どもの習い事や地域のサークルでは、多少の折れや使用感があるお札でも気にしないというケースが増えています。
最近では、振込やキャッシュレス決済に対応している教室も増えており、そもそも現金を渡さないということも・・・・・・。むしろ新札よりも毎月忘れずに支払うことのほうが大切です。
どうしても気になる場合は、先生に直接確認してみるのがおすすめです。聞きづらいと思うかもしれませんが「お月謝はみなさん新札で用意されていますかの方?」と一言たずねれば、むしろ丁寧な姿勢として受け取られるはずです。
先生に聞きにくければ、同じ教室の生徒さんに尋ねてみても良いかもしれません。
結婚式や葬儀には慣習としてのルールがある
習い事よりもっとマナーが大切にされる場面といえるのが、冠婚葬祭です。結婚式や葬儀にも、お金のマナーがあります。
・結婚式は新札
結婚式のお祝いは、新札を包むのが基本です。これは「結婚する新しい門出を祝う」という意味を込めているためで、折れ目や汚れのない新札を銀行で両替して用意しておくのが望ましいとされています。結婚式は事前に日付が解っているため用意しておくことができます。あわてて当日になって仕方なく使用感があるお札を包むといったことがないようにしましょう。
そして、結婚式のご祝儀袋は華やかなデザインが多いですが、いくらご祝儀袋が立派でも中身のお札がボロボロだとマナーがない人と思われてしまうかもしれません。
・葬儀は新札を避ける
葬儀の香典をお渡しする場合は、新札を避けて使用されている慣習です。理由は、新札は基本的に両替をして用意しておくものと考えられます。葬儀に新札を包むということは「前もって用意していた=不幸を予測していた」と受け取られてしまうのです。これは、ご遺族に不快な印象を与える可能性があります。葬儀では、多少使用感のあるお札を用意するのが一般的です。
新札しかないという場面は稀ですが、もし新札しか手元にない場合は両替をするか、もしくは折り目をつけて包むようにするという人もいらっしゃいます。
まとめ
現金を渡すときには、意外と細かいルールやマナーがあります。習い事のお月謝の場合は、必ずしも新札である必要はないというところが増えていますが、できるだけきれいなお札を選び、専用の月謝袋や封筒に入れて渡すのが丁寧です。気になる場合は確認することで、無用な不安を避けられるでしょう。
一方、結婚式や葬儀のような冠婚葬祭では常識や慣習としてのマナーが存在します。結婚式では新札を用意します。そして、葬儀では使用感があるお札を使うのがマナーです。
このように、場面ごとに正しいお金の扱い方を知っておくことは、相手への配慮や自分の評価につながります。普段はあまり気にすることがないかもしれませんが知っておいて損はありません。