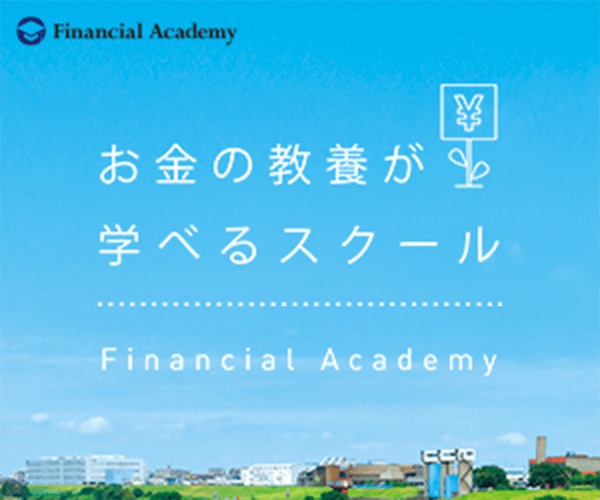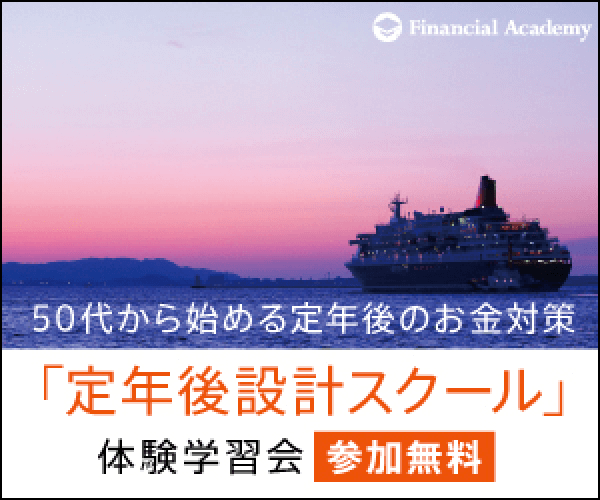こんにちは、億持ってない億男です。
近年、SNSなどで話題になっている「相席ブロック」という言葉をご存じですか?
高速バスや深夜バスを利用する際に、隣の席に知らない人が来ないようにするため、あえて連続する2席を予約し、直前で片方をキャンセルして隣席を空けるという行為です。
たしかに、長時間の移動で知らない人と密着して座るのは気まずいこともあります。
しかし、この「相席ブロック」賢い工夫などではなく迷惑行為であり、場合によっては法律に触れる可能性 もあるのです。
この記事では、相席ブロックとは何か、なぜ問題視されているのか、そして最悪の場合どのような犯罪になる可能性があるのか解説します。
高速バスや深夜バスでの相席ブロックとは
相席ブロックは、主に高速バスや夜行バスなど、長時間乗車するバスで公共交通機関で行われる行為です。手口としてはシンプルです。
・2つ並んだ席を予約する
・乗車直前まで両方をキープしておく
・出発直前に片方をキャンセルし、隣を空席にする
これにより、利用者は「1人なのに2席分使う」という自分にとって心地が良い状態を作ろうとしているのです。
この相席ブロックをすると、隣が空席になる可能性は確かに高くなるでしょう。ですが、本来その席を利用できたはずの人が乗れなくなりますし、バス会社は売り上げを落とすことになります。
つまり、相席ブロックは 「席の不正占有」 にあたる行為であり、明確な非常識行為といえます。軽い気持ちで「隣が空席だと楽だから」と相席ブロックをしてしまったというケースもあるかもしれませんが、実はバス会社にとっては大迷惑なのです。
相席ブロックの対策で手数料を値上げするバス会社も
相席ブロックをする背景には「できれば一人で座りたい」という乗客側の気持ちがあります。確かに、高速バスや深夜バスは長時間の移動になるため、隣席との距離感が気になる人は少なくありません。
しかし、一見ただの工夫に見える相席ブロックは、バス会社からすると 本来販売できたはずの座席が売れなくなるわけでありバス会社としては避けるべき事態です。そのため、バス会社側は対策としてキャンセル料の引き上げをしています。
キャンセル料が高くなれば「直前で片方だけキャンセルする」という方法自体のコストが上がるため抑止になるのです。
また、単に手数料を値上げするだけでなく女性専用のエリアや参列シートのバスの導入など「相席が不安だから避けたい」というニーズ自体に応える努力もしています。
バス会社は顧客のニーズを理解した上で対応を進めているのです。
偽計業務妨害罪に?
相席ブロックは、場合によっては 偽計業務妨害罪(刑法233条) に問われる可能性があります。
偽計業務妨害罪とは、嘘や偽装、または他人をだます行為によって企業や店舗の業務を妨害した場合に成立する犯罪を指します。刑法で規定されているためもし偽計威力業務妨害に問われると刑事事件ということになります。
相席ブロックの場合、表向きは「通常の予約とキャンセル」に見えます。しかし、はじめからキャンセルすることを前提に席を予約していた と判断されれば、それは「バス会社の正当な座席販売という業務を妨げた行為」とみなされる可能性があります。
偽計業務妨害は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。これは、決して軽い処罰ではありません。さらに、同じ方法を 繰り返し行っていた場合、「常習性がある」「悪質である」と判断され、より重く扱われる可能性もあります。バス会社も連続して何度も相席ブロックをされると法的手段に出る可能性もあるでしょう。
偽計威力業務妨害だけでなく損害賠償請求される可能性もゼロではありません。
つまり、相席ブロックは「隣に誰か来てほしくないだけ」「ちょっと工夫した」「悪いとは思っている」と言い訳をしてもバス会社に損害を与える行為であり犯罪になる可能性があるのです。
まとめ
相席ブロックは、ただ「快適に移動したかった」という気持ちから生まれた行為かもしれません。しかしその裏では、他の利用者が乗れなくなってしまったり、バス会社が本来得られるはずの売上を失ってしまうといった問題が生じています。
そのため、相席ブロックは単にマナー違反というだけではなく、状況によっては偽計業務妨害罪や損害賠償請求の可能性がある、非常にリスクの高い行為です。
もしどうしても相席が不安な場合は、女性専用席が用意されている便を選んだり、追加料金を支払って隣席を確保できるサービスを利用したり、そもそも独立シートや肘掛けで区切られた車両を選ぶといった正式な手段があります。
公共交通機関は、多くの人が快適に利用するために成り立っている場所です。自分が安心して過ごせる方法を選びつつ、同時にお互いへの思いやりを大切にして乗車したいものですね。