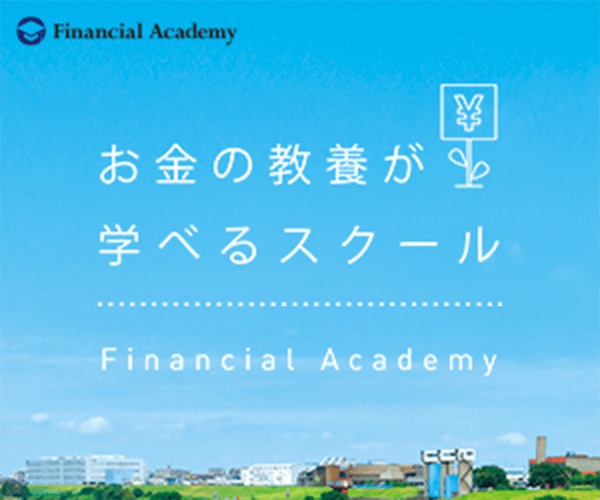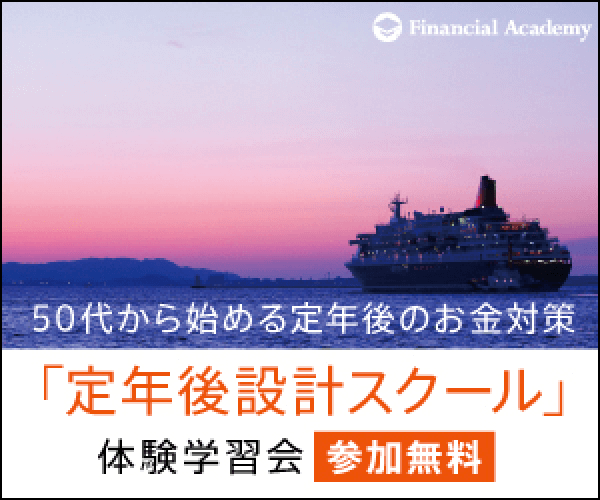こんにちは、億持ってない億男です。
「起業してみたい」「そろそろ法人化して仕事をしたい」と考えるときには、やはり資金のことがきになりますよね。お金がなければ起業はできないわけです。
そのようなときに、注目したいのが補助金です。補助金は返済義務がないものがあり「もらえるお金」というイメージがありとても魅力的に感じる人が多いと思います。しかし、補助金は、ただ「事業資金を援助して貰える」という仕組みではないのです。補助金を当てにしてビジネスを展開すると、思わぬ落とし穴が待っていることもあります。
今回は、これから起業を考える人に向けて補助金や助成金にフォーカスしてお話ししていきたいと思います。
補助金は活用できるものはしたほうがよい!
補助金とは、国や自治体といった公的機関が、特定の目的や事業に対して支給している資金援助のことです。多くの場合、返済の必要がありません。
補助金制度はとても多岐にわたっており、小規模事業者向けのものや、IT導入に関する支援、地域振興を目的としたものなど、目的に応じたさまざまな制度があります。
条件に合う補助金は最大限に活用するのが基本といってもいいでしょう。
ただし、補助金は「誰でも簡単にもらえる」というわけではありませんし、利用にあたっては注意したい点もあります。
補助金は後から支払われるタイプが多い
補助金を考える上で、最も大事なのが「お金の受け取りのタイミング」です。補助金は先に受け取ってから使うものではなく、原則として「対象経費を支出したあとに、その一部が補填される」という形なのです。つまり、先に資金を用意しておく必要があるのです。
つまり補助金は多くの場合が後払いということです。これを知らずに、補助金を「貰えるはずだ」という前提でビジネスを始めてしまうと、資金繰りがうまくいかなくなる危険があります。
また、補助金の多くには対象経費や期間」が決められており、条件から外れた支出には支給されません。書類も複雑なものが多く、申請後の審査も時間がかかるため、申請までに数カ月かかることもあります。
起業の資金は融資や自己資金が一般的
ビジネスに必要な資金は、自己資金や銀行融資で用意するのが一般的です。
自己資金は自由度が高く、最も適していると言えますが個人で用意できる金額には限界があります。その場合考えるのが「銀行融資」です。
日本政策金融公庫や地方銀行など、起業支援に積極的な金融機関では、創業者向けの金融商品が用意されています。もちろん、融資にあたっては事業計画書や見込み収支などを提出する必要はありますが、実績がないスタートアップ企業でも借りられる可能性は十分ありますし、創業のための資金を融資する制度もあります。事業資金は、金利も比較的低く、条件を満たせば無担保・無保証での融資も検討してもらえるケースがあります。
また、株式会社であれば「株式を発行して資金を集める」という方法もあります。これはいわゆる“出資を募る”という形です。
また、最近ではクラウドファンディングも注目されています。株を発行できない合同会社でも利用できるのがクラウドファンディングです。これは、新商品やアイデアに対して共感してくれた人から、インターネット等を利用して広く資金を集める仕組みで、個人でも使いやすいプラットフォームが増えています。資金を調達するだけでなく、新しいビジネスのテストマーケティングにもなるため、創業のさいのステップとして選ばれることも多い方法です。
このように、事業資金の準備の方法はひとつではありません。補助金はその中のひとつではありますが、スタート資金を補助金で・・・というと少し無理がでてしまいます。最初から補助金ありきですべてを考えるのではなく、全体の資金計画の中に補助金をどのように組み込むかを考えることが大切です。
まとめ
事業をしていくなかで、国や地方自治体の補助金は積極的に活用したい制度です。補助金は条件を満たしていれば、返済不要というケースが多く、事業の大きな支援となります。なので、条件に合う補助金はできるだけ利用したいものです。
しかし、補助金には「後払いであること」「条件が細かいこと」「申請手続きに手間がかかること」といった、性質があります。条件を満たしていればお金をすんなり貰えるというわけではありません。
補助金を最初からあてにするのではなく、ビジネスの中でうまく活かす必要があります。自己資金の軸はあくまでも自己資金や融資、クラウドファンディングなどです。補助金はそのプラスアルファの要素として捉えるようにしましょう。
補助金は「後払い」がほとんどですから、まずは自己資金や融資で必要な金額を用意して、その上で補助金を有効活用していきましょう。