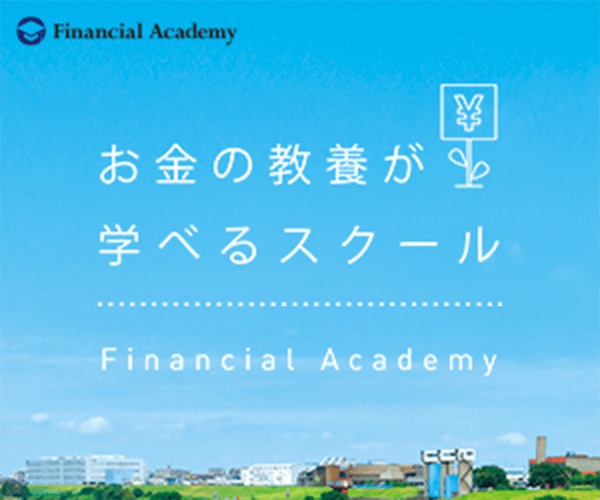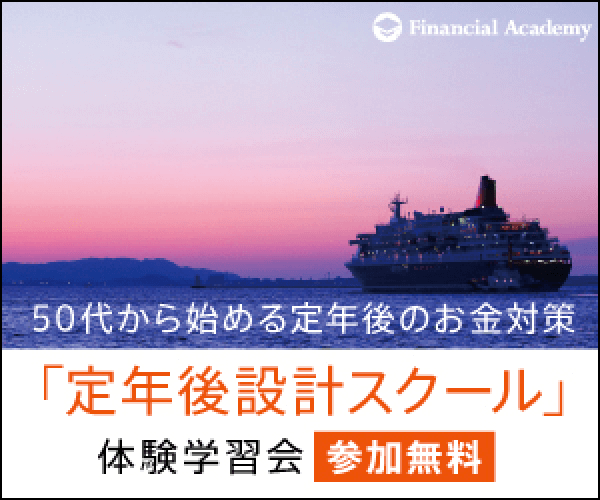こんにちは、億持ってない億男です。
訪問販売や電話勧誘などで、ついうっかり契約してしまった……。そんな経験がある人もいるかもしれません。そんなときに役立つのが「クーリングオフ制度」です。でも、「名前は聞いたことあるけど詳しくは知らない」「どういうときに使えるのか分からない」という人も多いのではないでしょうか。
この記事では、クーリングオフの基本的な仕組みから、対象にならないケース、悪質商法に巻き込まれたときの対処法まで、わかりやすく解説していきます。
クーリングオフとは?
クーリングオフとは、特定の取引において、契約後一定期間内であれば理由を問わず契約を解除できる制度です。冷静になって契約内容を見直すための「考え直す時間」を保証してくれる制度で、1976年に導入されました。
たとえば、訪問販売で強引に契約させられたとき、電話勧誘販売でよく分からないまま話を合わせてしまったときなどが該当します。そうした環境では、冷静な判断が難しいため、契約者を守るために「一定期間は無条件で契約を解除できる」というルールが設けられているのです。
クーリングオフが使えるのは、以下のような販売方法のみです。
● 訪問販売
● 電話勧誘
● 連鎖販売取引(マルチ商法)
● 業務提供誘引販売取引
● 特定継続的役務提供
上記のような販売方法で契約した場合であれば、申込書面又は契約書面を受け取った日から8日以内(マルチ商法は20日以内)に契約解除の意思表示を発送することで、クーリングオフで解約できます。
クーリングオフは通販では使えない
ここで気をつけたいのが「通販で買った商品にはクーリングオフが使えない」という点です。通販だけでなく店舗で購入した商品についても、クーリングオフは対象外となります。
たとえば、ネットショッピングやテレビショッピングで購入した商品に対して、「やっぱりいらなかったから返品したい」という場合、クーリングオフ制度は適用されません。これは、通信販売は「契約前にじっくり商品説明や条件を確認できる」ためです。電話勧誘や訪問販売の場合とは少し違うのです。店舗で商品を購入した場合も同様です。
ただし、通販サイト自体や店舗ごとに定めている返品ポリシー(例:商品到着後14日以内なら返品可など)があれば、それに従って返品することは可能です。そのため、通信販売を利用するときは、事前に「返品可能か」「返品の条件」「送料負担はどうなるか」などを確認しておくことが大切です。
参考サイト:独立行政法人国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen471.html
詐欺や悪徳商法の被害にあったら
詐欺や悪徳商法の被害に遭ったときに「クーリングオフ」が頭をよぎる人は少なくないでしょう。もちろんクーリングオフが使えるケースもありますが、前述したとおり販売方法によってはクーリングオフの対象ではないケースもあります。
つまり、詐欺や悪徳商法の被害に遭ったとき、「クーリングオフでなんとかなるのでは?」と思っても使えないこともあるのです。
もちろん、クーリングオフで問題が解決する場合もありますが、すべてのケースに使えるわけではありません。
以下のような販売方法の場合はクーリングオフは利用できません。
● インターネット取引(通信販売)
● 店舗での契約
● 契約後8日(マルチ商法の場合は20日)を過ぎている
● 商品がすでに使われたり、破損している
ただし、このような場合でも、何らかの対処が可能な場合があります。たとえば、詐欺的な説明や脅しによる契約だった場合は、「強迫」「詐欺」などを理由に契約を無効にできることもあるのです。
クーリングオフができないからといって、なにもできないというわけではないのです。
詐欺や悪徳商法の被害にあった場合は、クーリングオフだけにこだわらず柔軟な対応が必要です。できるだけ早い段階で、警察や消費生活センター、弁護士などに相談しましょう。
まとめ
クーリングオフ制度は、消費者を守るために作られた法律です。訪問販売や電話勧誘販売など、冷静な判断が難しい状況で交わした契約にのみ利用できる制度で、一定期間内であれば理由なく解除できるというものです。うっかり契約したけれど、よく考えたら・・・そんなときにはクーリングオフが利用できるかを確認しましょう。
ただし、クーリングオフ制度はどんな契約にも使える万能な制度ではありません。通販や店舗での契約などの場合は、時間経過に関係なくクーリングオフの対象外となります。そのため「クーリングオフが使える条件」と「使えない条件」を正しく理解しておくことがとても大切です。
また、悪徳商法や詐欺的な被害に遭ったときは、クーリングオフだけにこだわらない対応が大切です。状況に応じて、警察や消費生活センターや弁護士に相談し、適切な対応をとるようにしましょう。