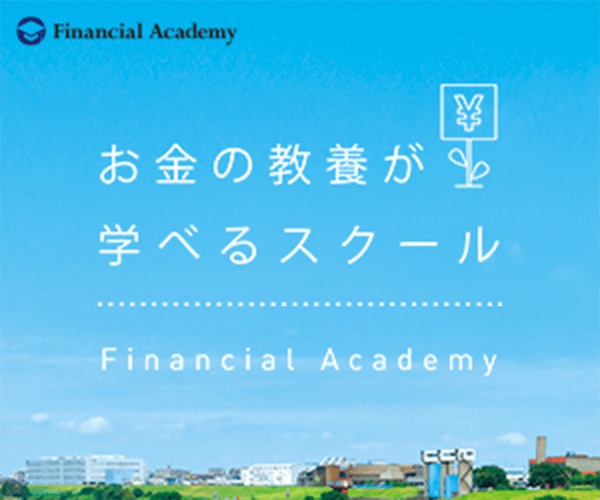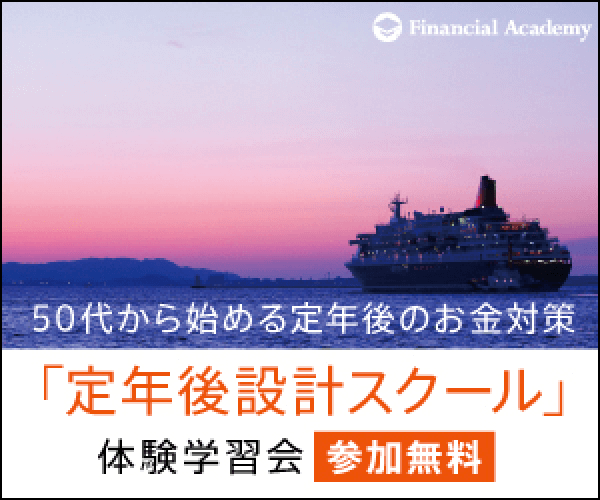こんにちは、億持ってない億男です。
夏が近づくと、お盆という言葉をよく耳にするようになりますね。亡くなった人の魂が、戻ってくるとされているのが「お盆」です。
実家に帰省したり、親戚と集まったり、地域によっては精霊流しや盆踊りなどもあって、古くから続く日本の行事として知られています。
ですが、お盆の法要となると楽しいだけでは済みません。場面によっては形式が重んじられるため、「これってどうするのが正解なんだろう?」と迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。
そして、悩みの種になるのがお盆のお香典に関するマナーです。
「いくら包めばいいのか?」「いつ渡せばいい?」「そもそも、お盆はお香典が必要なの?」今回は、失敗したくないお盆のお香典のマナーを解説します。
初盆とは
まず、お盆のなかでも特別な意味があって重要視されている「初盆」について確認しておきましょう。
「初盆」とは、故人が亡くなってから四十九日の法要を終えた後に、初めて迎えるお盆のことを指します。通常、お盆は毎年8月(地域によっては7月)に行われます。お盆の時点で、まだ四十九日が過ぎていない場合は初盆ではありません。
初盆は「亡くなったあと最初に迎えるお盆」ではなく「四十九日が終わったあとに初めて迎えるお盆」のことです。鑑定しやすいため覚えておきましょう。
初盆は、故人の魂が初めて自宅に戻ってくるとされているため普通のお盆より特別な行事となります。特に、ご遺族や親しい人にとっては大切な行事となります。初盆は、親族や故人と親しかった人たちが集まって、祭壇を作って抱擁を行います。初盆に関しては、通常のお盆よりも丁寧な形で行われるケースが多くなります。
当然ながら、こうした初盆の場面では、参列者であってもマナーや気配りも求められます。
お香典の金額にマナーがある
お盆のお香典はどのくらいお包みすれば良いのでしょうか。まず金額は、初盆なのか、それとも通常のお盆なのかによっても相場が少し変わってきます。
一般的に、初盆の場合は5,000円から10,000円がひとつの目安とされています。故人との関係性が近い場合は、多めに包む方もいらっしゃいます。一方で、初盆ではない場合は3,000円から5,000円程度がお香典の相場といわれています。
もちろん、大切なのは「無理のない範囲で」ということです。生活を犠牲にしてまで大きな金額をお包みする必要はありません。ですが、金額に関してはマナーがあります。
お香典に金額は、4,000円や9,000円といった数字は避けるのがマナーです。「死」や「苦」を連想させる数字は失礼に当たります。
また、初盆では法要のあとに食事が用意されているケースもあります。食事会に参加する場合は、会食の費用を考慮して数千円程度を上乗せして包むのが望ましいとされています。
この会食の費用をプラスするときに、4000円や9000円にならないように注意してくださいね。
初盆ではなくてもお香典はマナー
ここで注意したいのが、お香典は「初盆だけに持参するもの」ではないということです。初盆は特に重要とされていますが、たとえ初盆でなくても、亡くなった方のお宅にお邪魔してお線香を上げさせていただくのであればお香典を用意するのがマナーです。
そして、ここで迷うのが遺族から「香典はいらないよ」と言われるケースです。特に、遺族と親しい関係の場合は、そう言われることが多くなります。ですがそのようなケースでも、念のためお香典を準備して置く方がいいでしょう。遺族が本当に「お香典は必要ない」と思っていても、万が一、ほかの参列者がお香典を持参していたとしたら、自分だけが手ぶらだったという事態にもなり恥ずかしい思いをしてしまうかもしれません。
そのため「お香典はいらないよ」と言われていても、一応準備はしておいて、渡すかどうかは現地の雰囲気と他の方の反応を見て判断しましょう。
また、お香典はいらないと言われたけど「故人のために何かしたい」という場合は、故人が好きだったお菓子などをご仏前にお供えしてもいいでしょう。
まとめ
お盆は、亡くなった人の魂が帰ってくるとされる行事です。特に、四十九日法要を終えて初めて迎える初盆は特別な意味を持っています。
お盆にお線香を上げに伺う場合は、お香典を用意するのがマナーです。金額には一定の相場があり、縁起を担ぐ意味でも金額の選び方には気を配る必要があります。
お香典は、故人と遺族へマナーのひとつです。たとえ「お香典はいらない」と事前に言われた場合でも、何も持たずに訪れることに不安が残るなら、念のために準備しておくのが大人のマナーともいえるでしょう。
何より大切なのは、形ではなく心を込めて故人を偲ぶ気持ちです。形式にとらわれすぎる必要はありませんが、失礼がないように注意しましょう。